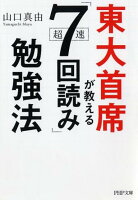どうもまこさん(@sHaRe_worlD_) です。
・どの教科のどの単元や範囲が得意で不得意なの?
・どの教科のどの範囲を重点的に勉強したらいい?
わからないところがわからないorz
って悩んでませんか??
勉強を進めているとこうした悩みに直面する人は多いです。必ずぶち当たるの壁と
この漠然とした迷走感
の解決を目指してまとめていきますよ
「わからないところをわかる」ようにするための要点は以下3点がポイントです
- 実力相応・以上の問題に挑戦する
- 間違え・ミスを「抽象化」する
- 「抽象化」した分野を復習する
キーワードは「抽象化」の部分ですね
それでは詳しくみていきましょう
スポンサーリンク
①:実力相応+ちょっと難しい問題に挑戦する
「わからないところ」を探し当てるには、より難しく大きなハードルに直面することが大切です
間違い=「わからないところ」
間違いこそが儲けなんです。自分のわからない所・苦手な所をさぐる上で大きな手がかりになります。なので、間違い=自分ができてないダメは受験生だ・・・なんて心配する必要はないですよ(プライドが邪魔しがち)
事実、「わからないところがわからない」人は意外と問題演習をしないままインプットだけで終わってしまうケースが多いです(実体験)
「わからないところ=間違ったところ!それを見つけるんだ!』」って自分に落とし込んで、大雑把にトライすることも時には大切ですね
「うりぁぁっ!!!」って東大の問題、MARCHの問題に挑んでみると、太刀打ちできるかできないか(自分の限界ライン)がわかりますよ。こうして限界ラインを探ってみましょうね😌
基本原則:難しすぎる問題は意味ないです
受験では相応+少し難しいくらいがベスト
それ以上の難易度は基本的に意味ないです
受験=RPGのレベル上げと僕は頻繁に例えてまして、以下をみてもらうとわかりやすいです
-
RPG:初期装備と0レベルからコツコツと敵を倒してレベルを上げて、さらに強い敵に挑んで、クリアを目指す
-
受験勉強:受験の科目について0から始め、基本を少しずつマスターして、応用問題も解けるように、そして受験の合格を目指す
共通するのは「自分のレベルに見合った、ほどよい強さの敵を倒し、経験値を多くもらってレベルを上げること。強すぎる敵は要注意」という点
つまり
「今日から東大目指して見るンゴ。まずは過去問からやりましょか」
は最悪なんですねww
いきなりラスボスに挑んでも何も得るものも無く大敗するだけです(チーン)
関連:浪人の伸びないタイプ?伸びるタイプ?【「伸びないわけがない状態」を目指せばOKです】
で、 もう一度この手順をおさらいすると..
- 実力相応+少し難しい問題集に挑戦する
- その問題での間違いにチェックつける
- チェック=「わからないところ」であると認める
です!
できるorできないの限界ラインを探ることがポイントですね
スポンサーリンク
②:間違い・ミスを「抽象化」する
実力以上の過去問・問題集にチャレンジした時に、必ず間違い・ミスがでてきます
これが君のわからないところ!
上に書いたように、間違えた・ミスした問題が「お宝」です
大切なのはここからの「抽象化」の工程です
その手順は以下の通り!
- 間違えた問題にすべてチェックする
- そのチェックの問題の解説を読む
- 「どの分野・単元」の問題かを特定する
これが「わからないところの」抽象化の手順です
例えば、英語の文法問題を間違えてチェックをつけてたとします
その問題から「分野・単元」を特定します
もっと詳しくいえば、間違えた問題は参考書のどの単元の何ページに書かれているのかを特定します
文法問題の中でも、仮定法、倒置、省略など様々ありますが、この単元を特定しましょう
これがひとつの具体的な問題の「抽象化」の手順です
*この記事から本ブログを知ってくれた人もいるでしょう
具体的な勉強で使う参考書について、国語・英語・社会科目の独学勉強方法たちはすでに以下に僕がまとめてあります
レベル順にまとめたので、迷いは無くなるかと思います😌
③「抽象化」した分野を復習する
ここまできたら後はやるだけ!
「わからないところ」がわかるようになりました(判明)
次は「わからないところ」をわかるようにすることです(理解)
何度も参考書・教科書を読んで理解に努めましょう
読み終わった後に、間違えた問題にもう一度挑戦し、正解できるようになればパーフェクトです
*「わからないところ」の理解について、個人的なおすすめな方法はエアー授業です
エアー授業とは:自分が勉強したところを、自分に説明すること
です
インプットからアウトプットまでを自分で完結できるものすごく効率の良い方法で効果はめちゃくちゃあります
騙されたと思ってやってみてくださいね😌
ひとまずこの手順にて「わからないところ」が「わかる」ようになります。あとはどんどん取り組んでコツをつかんでいきましょうね
関連:【レビュー】『身の丈に合った勉強法』を読んでみた感想!効率の良い勉強とはどんなもの?
補足:勉強方法に関する本を読み漁る
「少し難しめの問題演習」と「間違い・ミスの抽象化」が、わからないところがわからない現象の突破口であると説明しました
それでも
「ど〜うしても無理だ!どうしたらいいかもうわからねえよ!勉強方法が根本的にだめなのかも・・・」
という事態の可能性もあります。そこで
- 「勉強方法」に関する書籍を読み漁る!
- 「良い!」と思ったところだけパクる!
- 「違う」と思ったところは無視!
を試してみてください。先人の知恵を徹底的にかりましょう
具体的には、高レビューの本たちをアマゾンで検索して順番に読んでいく、という流れです
「良かった!」とみんなが評価・レビューする本には信憑性・信頼性があります
単純明快でシンプルすぎる方法ですが、勉強方法の軌道修正のきっかけになり、僕にとってものすごく効果的でした
下記の4冊は僕が最近読んで「良かった!!」と思える本でしたので参考までにどうぞ😊
東大主席の人の勉強方法の本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1分間の短期記憶を活用する術の本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
「思いだす」にフォーカスした本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
脳のメカニズムからアプローチする本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ザーッと一読すると、「これが足りないなあ!」「これを真似してみよう!」 と思える内容に出会えるはず
読了後はすぐに実行にうつしてみましょうね
まとめ:「わからないところ」をなくす=勉強
勉強で「わからないところがわからない」現象を打破する方法をお伝えしました
まとめると...
- 実力相応・以上の問題に挑戦する
- 間違え・ミスを「抽象化」する
- 「抽象化」した分野を復習する
ミスの「抽象化」が肝になりますね。
この「抽象化」ができる学生は「わからないところ」をどんどん潰していけるため、みるみる成績が上がっていきます
勉強はこのように「わからないところをどれだけ無くせるか?!」のゲームのようなものです
後は、やる気と根気と体力があれば、誰だって受験を突破できます
ぜひ参考にして、受験勉強に応用して下さいね!
スポンサーリンク
余談:勉強以外にも活かすべし
こうした間違い・ミスの「抽象化」は勉強以外・学生以外の人生にも有益です
- 将来にかけて、自分のやりたいことが、わからない。
- 自分は今何に悩んでいて辛いのか、わからない。
- どうして私は生きているのか、わからない。・・・
大きなくくりですが、この問題は『自己分析』に関わります
「やりたいことがわからない」
これは就活生のあるある問題ですが、そんな時こそ過去を抽象化して、未来を具体化するといいです
- 大胆に大きな目標、課題設定を試みたり(具体化)
- 自らの記憶の”基礎”つまり原体験や過去の思い出を掘り下げたり(抽象化)
ですね!
- 「わからないところがわからない」現象や
- 「やりたいことがわからない」現象
に直面した時に試してみて下さい
きっと打破できるはずですよ〜〜それではっ😄
人気記事:【2020年度版】おすすめオンライン家庭教師+動画授業を7つ紹介!【オンライン家庭教師のメリットは無限大です】