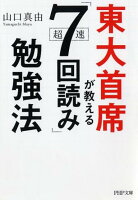こんにちは、まこさん(@sHaRe_worlD_) です。スランプは真剣な努力家の証だぞーーー!!
本記事では
「受験生です。この前の模試では成績が急に下がってしまいました・・・。勉強してるのに下がってしまった...。このスランプから抜け出す方法を教えて😭」
と、悩む受験生に向けてまとめます!
頑張ってるのに報われない。。これほど辛いことはありませんよね・・・受験生の頃、幾度なく経験しました。その経験と指導の経験を合わせてまとめていきます😌
スポンサーリンク
- 前提:”正しくない”努力は嘘をつく
- スランプ脱却法①:もう一度「基礎・基本」を確認する
- スランプ脱却法②:少し難しめの問題演習をする
- スランプ脱却法③:勉強方法に関する本を読み漁る
- まとめ:受験勉強のスランプは「成長痛」
前提:”正しくない”努力は嘘をつく
受験を振り返って感じたのは、ダルビッシュ投手の以下の言葉は、勉強にもあてはまるのが現実。ということ
練習は嘘をつかないって言葉があるけど、頭を使って練習しないと普通に嘘つくよ。
— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) 2010年6月11日
わかりやすく整理すると以下の通りです
- 闇雲な努力:とりあえず英語やろう。まずは辞書の先頭から全て覚えてやるわ。気合いがあれば何でもできる!!!!
- 適切な努力:今の自分に足りないのは語彙力。自分のレベルに合う参考書をみつけて、1日50個ずつ覚えよう。明日はまた20個忘れるからしっかり復習しよう
極端な例を用いましたが、こんな具合です
前者をみると、そりゃあ〜伸びないっしょ笑と思えますよね
「スランプ(伸び悩み)」を抱えている今、自分の勉強を振り返ってどう感じますか??
ここで最も危険なのが
「大丈夫。努力は絶対裏切らない。信じる者は救われる。絶対に。」
と、信じ込んで全く的外れな勉強してる人です
自分では勉強の最中に気づかず、蓋を開けた時(模試終了後)にそのヤバさに戦慄するパターンです
うん。嫌ですよね
そこで、スランプを極力避ける前提として「今やってることは正しい適切な努力なのか?」のように批判的に考える姿勢がとても大切です
▼特にね、僕自身第一志望の慶應大学を目指すにあたって伸び悩みました
「伸び悩み」が前提ではないですが、目指す上での心がけを以下にまとめてあるので参考にどうぞ😌
関連:浪人生が早慶(早稲田・慶應)を合格するためにやりたいこと・心がけたいこと【文系学部志望の人に向けてまとめます】
前置きはさておき、受験生の頃どのようにスランプを脱却してきたのか、じっくり解説します
以下の3つが要点になります
- もう一度「基礎・基本」を確認する
- 少し難しめの問題演習をする
- 勉強方法に関する本を読み漁る
そっかーわかったー!と思うマインドだけでは自己満足で明日には気持ちは飛んでしまってます
読了後はすぐに行動・実行にうつすことをおすすめします😌
スポンサーリンク
スランプ脱却法①:もう一度「基礎・基本」を確認する

「うしうし、成績上がってきてるし面白いなあ!次の参考書にガンガン進めていこ!」
ってノリノリにモチベ高く勉強を進めていたのに
模試結果「マイナス30点・・・まじかよおい^q^」
全然あると思います
「辛すぎワロタ」なんて言葉の50倍辛いです
どうして下がる?スランプに陥るのか?
を考えます
「段階的成長」の認識が足りない説
受験勉強はRPGと同じ!と僕はよく言います
-
RPG:初期装備と0レベルからコツコツと敵を倒してレベルを上げて、さらに強い敵に挑んで、クリアを目指す
-
受験勉強:受験の科目について0から始め、基本を少しずつマスターして、応用問題も解けるように、そして受験の合格を目指す
共通するのは「自分のレベルに見合った、ほどよい強さの敵を倒し、経験値を多くもらってレベルを上げること。強すぎる敵は要注意」という要素
これが正しい努力=段階的成長
の裏付けになります
超極端な例ですが
「今日から早稲田大学目指して見る。まずは過去問演習からやるンゴ」
見事な空振りなのは理解できますよね
つまり
- 今の自分のレベルを直視する「現状把握力」
- 基礎から発展、応用へ段階を踏んで勉強を進める「計画力」
- 模擬試験の結果から苦手な部分を強化・補強できる「柔軟性」
の3つはRPGも受験勉強でも活きる能力です
「スランプ(伸び悩み)」に陥ってしまうのは、上記3つのどれかの能力が足りてない可能性が大きいのです
つまr、今の自分に”適切でない”勉強をやってる可能性が高い、ということですね(=平気で嘘をつく練習・努力)
結果「やってるけど伸びない人」の状況におちいってしまいます。僕自身も経験しました
じゃあどう打破するのさ??
って所ですが
基礎・基本に戻ってみよう
と言えるでしょう
どの科目も基礎→応用・発展→過去問の段階を踏んで進めていきますが、気付かぬうちに基礎が抜けてることが多くあります
基礎が抜けたまま次の問題集をやってしまう。基礎が抜けてしまっては、レベル上げた参考書の勉強も空振ってしまいます
英語で単語が抜けてるのにもかかわらずちょいレベル高い長文の問題集をやるようなもの。段階的成長の無視になりますね
でも....
基礎に戻るって後退して進歩がない自分を認めてるみたいでしんどい...と思ってしまう・・
そんなこと思う必要は一切ありません
「基礎・基本に戻る」は後退してるわけじゃない
からです
僕の指導と受験の経験で、最後まで成績を伸ばし続けた人は、基礎・基本、基礎レベルの問題を繰り返し続けて自分の立ち位置を常に把握しています
むしろ難関校に合格できた学生は皆「基礎基本の大切さ」を力説します
彼らは「できたから!!もうOK!!もういいや!」のように簡単に終わらせず、繰り返し無限リピートしてます
例えばこんな一問一答はもはや神の領域です
今年のセンター世界史で満点を取った生徒の「東進一問一答」。もはや原形をとどめず、凄まじいオーラを放っている。 pic.twitter.com/a3S5ZWqXx8
— 鈴木悠介 (@yuusuke_suzuki) 2018年1月16日
受験生でスランプになるのは何もおかしくないこと
まずは基礎基本の本にもう一度戻って覚えてるかどうか確認してみましょう😌
▼国語・英語・社会科目の独学勉強方法たちはすでに以下に僕がまとめてあります。適宜参照しつつ「正しい努力」の構築を目指しましょうね
スランプ脱却法②:少し難しめの問題演習をする
いや、基礎・基本も全部できてるんだけど???なんで?スランプになる???
という感じの人もいるはず
基礎・基本ができてんのに伸びねーじゃんか!どうしてだ?!
このパターン、困りますよね〜
僕は受験を「RPG」を見立てててました。「RPG」でうまーーーいレベル上げは、そこそこ強い敵を倒して多めの経験値を稼ぐこと
これを勉強に応用します
今の実力にとって少し難しめの問題(例えば、問題を解いた時に70%くらいの正答率)を解いてみましょう
これはすぐにできるかと思います
大切なのはここからです
「ミス」を観察→「抽象化」する
「抽象化」と聞くとなんか難しそうな気がしますが、一言でいうと
「どの本のどの単元のどのページに戻って勉強するとミスをカバーできるか」
を明確にすることです
「課題の抽象化とその解決の高速サイクル」は日本の大学受験のコツです😌
— まこさん@世界史ブロガー (@sHaRe_worlD_) 2019年3月17日
つまり、科目問わず問題演習でミスした時に「どの本のどの単元のどのページに戻って勉強するとカバーできるか」を知っている知っていないでは雲泥の差が開きます。小難しいけど「抽象化力」を受験生は養おう😌🌸
「抽象化」の簡単な例を挙げますね
2017年の京都大学の世界史の入試問題をみてみます。こちらは一問一答形式なのでそこまで恐ることはありません😌

なんとなくやってるよ!と無意識にやってる人もいると思います
このスランプの時期では”意識的”に行うよう心がけてくださいね
手順を言葉で整理すると下記の通りです
- 何も見ずに問題演習にチャレンジ
- ミスにきちんと印をつける(誤魔化さない)
- 「どの本の」「どの単元の」「どのページ」に戻るとミスをカバーできるかをじっくり考える
- その単元のページを復習・付箋をはる
- 翌日ももう一度復習する
言わずもがな大切なのは3番目の手順です
この京都大学の例題では「文化史の中国」が抽象化され復習のポイントがわかりました
このサイクルを特に伸び悩む科目に応用させていきましょう
でも、ある程度できるようになると「もうワイは絶対合格するでー!余裕やでー」と余裕ぶってしまうのはわかりますw僕も同じでした(現実はそうでもないのに←)
上記の頃は特に難しめの問題ミスに取り組んで「不出来」に直面するのが怖いです。なぜなら自信喪失の可能性があるからですね...
「不出来」の直面はスランプの時期は、とても辛いですが、躊躇いやメンタルブロックを壊す勇気を持ちましょう
「新しくやるべきことを見つけるため。ってかそれがスランプ脱却!成長するステップだ!!ミスは儲けの証だー!」
と、自己洗脳するのも有効です
試せる人はぜひ直ぐに試して下さいね。きっとスランプ(伸び悩み)の解消に繋がります
スポンサーリンク
スランプ脱却法③:勉強方法に関する本を読み漁る
伸び悩んだ時には「基礎・基本の立ち返り」と「少し難しめの問題演習」でスランプの脱却ができる!と、ここまでまとめました
それでも
「ど〜〜〜うしても無理だ!どうしたらいいかもうわからねえよ!勉強方法が根本的にだめなのかも・・・」
という時がやっぱりありますね
僕の反省ですが、この時は「今が絶対!!」と想像以上に強く思い込んで頭が凝り固まってる可能性があります
「これじゃあいつまでもスランプだ・・」
と切羽詰まった思いの僕がやったのは
- 「勉強方法」に関する書籍を読み漁る!
- 「良い!」と思ったところだけパクる!
- 「違う」と思ったところは無視!
です
高レビューの本たちをアマゾンで検索して順番に読んでいく流れです
「良かった!」とみんなが評価・レビューする本には信憑性・信頼性があります。単純明快でシンプルすぎる方法ですが、ものすごく効果的でした
下記の4冊は僕が最近読んで「良かった!!」と思える本でしたので参考までにどうぞ😊
東大主席の人の勉強方法の本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1分間の短期記憶を活用する術の本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
「思いだす」にフォーカスした本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
脳のメカニズムからアプローチする本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ザーッと一読すると、「これが足りないなあ!」「これを真似してみよう!」 と思える内容に出会えるはず。すぐに実行にうつしてみましょうね
「なんかなあ。これでいいのかなあ...不安だなあ」と悶々とする気持ちは、いつ襲ってくるかわかりません💦
スランプ(伸び悩み)以外の時でも、勉強の方向性の微調整ツールとして活用してみて下さいね!
スポンサーリンク
まとめ:受験勉強のスランプは「成長痛」
偏差値が30→40→50→60→70→75のように綺麗な伸びを描く人はほと〜んどいません
いないことはないですが、例外的な受験猛者です
むしろ「受験で上手くいった!第一志望の大学に合格できました!」って人の大半は
「受験までの道のりでスランプ(伸び悩み)に直面したよ!でもその都度クリアしたよ!」
って人です
「自分だけが、、できない。受験に向いてないのかな・・・」と落ち込む必要は全くないです
むしろ
スランプ(伸び悩み)は必ずやってくるクエスト
と捉えておくといいです
この心構えができると「ほら〜〜やっぱりきたきたきた」と、現実を直視し冷静な判断+解決に向けた行動もできます
スランプ(伸び悩み)を成長痛と捉え、その都度都度考え抜き精進していきましょうね
今まさにスランプの渦中にある人は、直ぐに行動を起こすことをおすすめします
「今やってるのは”適切な”努力なのか?」と、批判的に考えることを起点としてくださいね
それでは、本記事が受験生にとって良い方向に転じるきっかけとなれば幸いです😌✨
人気記事:【2020年度版】おすすめオンライン家庭教師+動画授業を7つ紹介!【オンライン家庭教師のメリットは無限大です】