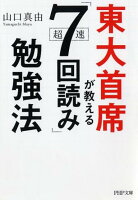こんにちは、まこさん(@sHaRe_worlD_) です。僕は浪人を1年経験しました・・が・・伸び悩んだ時期がありました
本記事では「浪人で今伸び悩んでる....どうすべきか....わからない...」という人に向けて僕の経験をもとに書いていきます
スポンサーリンク
前提:「セルフブラック」の浪人
セルフブラックとは、世間のブラック企業の個人経営バージョン。それが転じ、浪人バージョンの「セルフブラック」になります
いわゆる
- 長時間労働
- 超絶理不尽
がブラック企業の2大特徴ですね
しんどい以外のなにものでもないですが、これをセルフ(自身)に 課す、というものが浪人です
僕自身、勉強時間は基本13時間以上は毎日やって(長時間労働)、模試では想像の10倍以上に下がった時もありました(超絶理不尽)・・
長時間労働・超絶理不尽の目にあう期間が浪人です
暗闇のトンネルを走り続ける、そんな感覚に近いですね。最初の頃は勉強して「成績伸びてきたぞ〜〜!」と思っていても突然伸びなくなる・・・これも普通です
そんな時にどうする???
経験をもとに「伸び悩んだ時の解決法」を下記に3つまとめます
スポンサーリンク
①:もう一度「基礎基本」を確認する

「うしうし、成績上がってきてるし面白いなあ!次の参考書にガンガン進めていこーー!」ってノリノリに勉強を進めていたのに、模試結果
「マイナス30点・・・まじかよおい・・・」
全然あると思います。辛あああ!って感じ
どうして下がる?伸び悩むか?
受験では、どの科目も勉強は基礎から応用・発展、過去問の段階を踏んで進めていきますね
しかーし、気付かぬ間に基礎が抜けてる...という状況に陥ってしまうことがあるんです
そして基礎が抜けたまま次の問題集をやってしまう。基礎が抜けてしまっては、レベル上げた参考書の勉強も空振ってしまいます
英語の勉強で、単語が抜けてるのにもかかわらずちょいレベル高い長文の問題集をやるようなものです
でも....基礎に戻るって後退して進歩がない自分を認めてるみたいでしんどい...と思ってしまう・・
そこで明記したいのは
基礎に戻るは後退してるわけじゃない
ということ
最後まで成績を伸ばし続けた人は、最後まで基礎・基本を繰り返し続けてます
世界史の一問一答も
英語の単語・熟語も
「できたから!もうOK!」と終わらせずに繰り返し無限リピートさせてます
例えばこんな一問一答はもはや神の領域ですね
今年のセンター世界史で満点を取った生徒の「東進一問一答」。もはや原形をとどめず、凄まじいオーラを放っている。 pic.twitter.com/a3S5ZWqXx8
— 鈴木悠介 (@yuusuke_suzuki) 2018年1月16日
要は、浪人での伸び悩みは勉強が空振りしてる可能性がある! ってことで、基礎基本の本にもう一度戻って覚えてるかどうか確認してみる!
忘れていたらもう一度やり直して、基礎を叩き直す!受験本番までず〜〜っとですね。これは本当に大切なことです
▼各科目の「基本」については下記にまとめた記事に記載してあります。参考にしてみて下さいね
②:少し難しめの問題演習をする
いや、基礎基本も全部できてるんだけど???なんで??伸び悩む???
という感じの人もいるはず。基礎基本ができてんのに伸びねーじゃんか!!どうしてだ?!
このパターン、困りますよね〜〜
僕は頻繁に受験を「RPG」を見立てててました。「RPG」でうまーーーいレベル上げは、そこそこ強い敵を倒して多めの経験値を稼ぐこと、でいいですよね
これを勉強に応用しましょう
今の実力にとって少し難しめの問題(例えば、問題を解いた時に70%くらいの正答率)を解いてみます
これはすぐにできるかと思います
大切なのはここからです
「ミス」を観察し、抽象化しよう
「抽象化」と聞くとなんか難しそうな気がしますが、一言でいうならば
「どの本のどの単元のどのページに戻って勉強するとミスをカバーできるか」
を明確にすることです
「課題の抽象化とその解決の高速サイクル」は日本の大学受験のコツです😌
— まこさん@世界史ブロガー (@sHaRe_worlD_) 2019年3月17日
つまり、科目問わず問題演習でミスした時に「どの本のどの単元のどのページに戻って勉強するとカバーできるか」を知っている知っていないでは雲泥の差が開きます。小難しいけど「抽象化力」を受験生は養おう😌🌸
「抽象化」の簡単な例を挙げますね
2017年の京都大学の世界史の入試問題をみてみます。こちらは一問一答形式なのでそこまで恐ることはありません!

「ん?あたりまえじゃね?」と思う人ももちろんいるし、一方無意識でやってる人もいると思います
改めてこの手順を言葉にすると下記の通りです
- 何も見ずに問題演習にチャレンジ
- ミスにきちんと印をつける(誤魔化さない)
- 「どの本の」「どの単元の」「どのページ」に戻るとミスをカバーできるかをじっくり考える
- その単元のページを復習・付箋をはる
- 翌日ももう一度復習する
言わずもがな大切なのは3番目の手順です
この京都大学の例題では「文化史の中国」が抽象化され、復習のポイントがわかりました。このサイクルをどんな科目でも応用させていきましょう!
実際ね・・ある程度できるようになると「もうワイは絶対合格するでー!余裕やでーー」と余裕ぶってしまうのはわかりますw僕も同じでした
難しめの問題であえてミスに直面し、「新たなにやるべきこと」を見つけるこのが伸び悩み解消のコツなのです
スポンサーリンク
③:勉強方法に関する本を読み漁る
ここまでまとめたように、伸び悩んだ時には「基礎基本に立ち返り」と「少し難しめの問題演習」をすることでさらなる飛躍の準備ができます
それでも「ど〜〜〜うしても無理だ!どうしたらいいかもうわからねえよ!勉強方法が根本的にだめなのかも・・・」
という時には、頭が凝り固まってる可能性があります
僕がやっていたのは
- 勉強方法に関する書籍を読み漁る
- 「良い!」と思ったところだけパクる
- 「違う」と思ったところは無視
です。「良かった!」と皆が評価・レビューする本には信憑性と信頼性があります。単純だけどものすごく効果的でした!
その本たちをアマゾンで検索して順番に読んでいく、という方法です
下記の4冊は、僕が最近読んで「良かった!」と思える本でしたので、参考までにどうぞ!
東大主席の人の勉強方法の本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1分間の短期記憶を活用する術の本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
「思いだす」にフォーカスした本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
脳のメカニズムからアプローチする本
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
長時間勉強してると「なんかなあ。これでいいのかなあ...不安だなあ」と悶々とする気持ちを抱える時期があります
「伸び悩んで辛い」という以外の時でも勉強の方向性の微調整手段として活用してみて下さいね
スポンサーリンク
まとめ:伸び悩みは成長痛なんだ
いや、くさいいかよ
でもこれは本当です
偏差値が30→40→50→60→70→75のような綺麗な伸びを描く人はほと〜んどいません
いないことはないですが一部の例外的な受験猛者です
むしろ「浪人で上手くいった!第一志望の大学に合格できました!」って人のほとんどは、ゴールまでの道のりで伸び悩みに直面してるし、その都度クリアしています
自分だけじゃなく伸び悩みは必ずやってくる困難だと捉えておくこと!
そう心構えができると「ほら〜〜やっぱりきたきたきた」のように、現実を直視し、冷静な判断と解決に向けた行動もできます
伸び悩みを成長痛と捉え精進していきましょう。参考になれば幸いです!
補足:オンライン家庭教師は浪人に最適!
オンライン家庭教師に馴染みのある人は多くないのではないでしょうか??
僕自身、オンライン家庭教師として小学生・中学生の社会+高校生の世界史の指導をしています
ここで最後に、オンライン家庭教師は塾よりも”圧倒的”にコスパ最強だな!と本音を暴露させてください
なんせ、、マンツーマンで超難関大学の先生に指導してもらえるのだから・・・
具体的なオンライン家庭教師(オンライン個別指導)のメリットは
- 近くに塾・家庭教師がいなくても大丈夫!(どこでも)
- 部活での帰りが遅くても大丈夫!(先生次第でいつでも)
- 講師への交通費支払い、気遣い(掃除やお茶出し)などしなくても大丈夫!(コスト削減)
- 東大・早稲田・慶應大学の先生に教えてもらえる!(講師のクオリティ高過ぎ)
などですね!
加えて塾の学費の約4分の1〜3分の1程にまで抑えることができるのはオンラインならではの魅力
控えめに言っても冷静に、、東大京大、早稲田慶應の現役学生の先生欲しくないですか?(僕の受験生の頃に欲しかった...)
総じて、塾よりもリーズナブルかつ超難関校に在籍する先生に指導してもらえるオンライン家庭教師は超革命的なサービスです
中でも厳選の3つのサービスを以下にのっけておきますね😌”無料”でお試しできるので、伸び悩んだタイミングの相談につかってみてくださいね
- Netty(ネッティー)※早稲田・慶應大学の先生が多く在籍。無料体あり!
e-Live(イーライブ)※勉強のやり方から解説まで!東大生講師多数在籍。無料体験あり!
- ディアロオンライン※Z会のオンライン家庭教師サービス。受験対策に超定評のあるZ会なので安心!無料相談あり!